梅雨空の中、連日ご契約済みのお客様の物件お引き渡しで、忙しく
しております、REDSの坂爪です。
さてさて、昨今ご購入希望のお客様のご案内をしておりますと、
お客様からご質問頂くのが「2022年の生産緑地問題」です。
特に、一戸建てをお探しのお客様からは、後3年待ては、安く
なるのではないか?
というお話を頂く事が多くなりました。
生産緑地制度自体は、1992年に指定が開始された制度で、都市部
の環境保護等の観点から制定され、生産緑地として指定を受けると、
農地として、その土地を利用する代わりに、税制面でのメリットが
得られるという制度。
但し、これには義務(条件)が御座います。
「生産緑地として、税制面の優遇を受ける為には30年間、その
土地で農業を営んでください」と言う営農義務が課せられて
居る訳です。
そうなんです、1992年に多くの土地が生産緑地として指定を受け
ました、生産緑地全体の8割程度が1992年の指定と言われています。
そこから30年の2022年・・・
税制面の優遇がなくなる・・・・
農業の後継者不足・・・
等の問題も相まって、生産緑地が一斉に手放され、それによって
相場が下がるのではないかと言われている訳です。
しかし、不動産業界で仕事をしているものの感覚としては、
2022年→ハイ!!値段下がりました。
とは成らないののでは無いかと思っています。
何故なら、土地は駐車場や、アパート用地、店舗用地などなど
沢山の運用・活用方法があります。
自分が地主で有ったと想定すると、「売る」事よりも、「運用」
を第一に考えるでしょう。
手放してしまえば、一時のお金は入りますが、それ切りです。
また、多くの地主さんは、先祖代々受け継いだ土地で、土地に
対する思い入れのある方が多数です。
そう簡単には手放しませんし、手放すのであれば、それなりの
金額で無ければお譲り頂けないでしょう。
そんな訳で、2022年の生産緑地問題、おそらくは2022年・
2023年に直ぐに相場が下がる様な事は無く、影響が出ると
しても10年単位のお話になるのでは無いかと思っています。
また、元々は都市部の環境保護の観点から制定された制度、
その立法趣旨を考えると、都市の環境保護はこれまでも、
これからも大変重要なテーマです。
実際、都内の城西エリア等のご案内で、ふと生産緑地の
トマトやトウモロコシを見かけると、長野県育ちの私は、
田舎の祖父母の畑を思い出して、ほっこりします。
個人的には、畑はやらなくても良いですが、緑は残して頂き
たいと思います。
不動産営業マンとしては、不動産取引が増えるのは嬉しい
事ですが、都市部・都市周辺の住宅街に緑のある環境を
維持する事も大切だと考えます。
一度、建物が建ってしまった土地が再度緑地化される事
は殆ど期待できません。
何か良い方法は無いですかね??

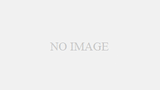
コメント