REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郞です。
不動産の購入や所有後、特に気になるのは「不動産価格がこの先どう動くのだろう」という点ではないでしょうか。不動産価格は、一般に築年数が進むにつれて低下していきます。この変動の仕組みを理解しておくことは、購入・売却時の重要な指針となります。
今回は、不動産価格がどのように推移していくのかについて解説します。

(写真はイメージです)
不動産の耐用年数と価値の目安
不動産は、いつまで住める家なのかという意味での耐用年数として目安があります。これとは別に、建物の構造上で見た価値を表す法定耐用年数(税法上の建物価値の基準)という基準値が定められています。
戸建てとマンションについてそれぞれ解説します。
戸建ての場合
戸建ての耐用年数の目安は、木造で約30年、鉄骨造で約30~50年、鉄筋コンクリート造で約40~90年とされています。現代は木造でも耐久性の高い素材や、耐震技術も進化しているため、築30年以上でも問題なく住み続けられる物件が増えています。
一方、法定耐用年数は築22年となっていますが、住めなくなるという訳ではなく、築22年で建物価値が帳簿上「ゼロ」になるという意味です。つまり、築22年で売却を検討したときに、建物代がゼロとなり土地代だけが残っていることになります。
マンションの場合
近年のマンションはメンテナンスやしっかりとした維持ができていれば、築120年程度でも住み続けられることが可能です。
ただし、法定耐用年数は鉄骨鉄筋コンクリート造で47年。築47年を過ぎると、建物の帳簿価値がゼロになります。
不動産価格の築年数別推移
建物が古くなれば劣化が目立つようになり、物件価格も下落していきます。建ってからの年数と価格の推移を知っていると、購入するタイミングや売却するタイミングが計画しやすくなります。ポイントを解説します。
戸建ての価格推移
- 購入直後:1日でも人が住んだ時点で中古物件になり、価値が急落します。
- 築5年:外観や内装、設備などがまだ新しくても約20%の下落があります。
- 築10年:最大50%前後まで下落します。
- 築15年:25~35%程度の価格は維持できます。
- 築22年以降:建物価値はゼロとなり、土地代のみが残ります。
マンションの価格推移
- 購入直後:戸建てと同様に、住み始めた時点で中古物件の扱いになります。
- 築5年:10%程度の下落。
- 築10年:新築価格から20%程度の下落。
- 築11~15年:25%の下落。
- 築16~20年:35~40%の下落。
- 築21年目以降:大きな価格の下落はなく、横ばいを続けながら少しずつ下がっていきます。
注意するべき不動産価格の変動要因
築年数による価格の推移を解説してきましたが、すべての物件が建物の年数による推移に当てはまる訳ではありません。立地や周辺環境の影響を大きく受けます。
再開発エリアや近年のような不動産市場の上昇トレンド下では、築年数にかかわらず値上がりするケースも珍しくありません。特に、都心部や交通アクセスの良い駅の駅近物件のような好立地であれば、建物が古くなっても人気が落ちず、価格を下げずに売れていく傾向があります。
一方で、駅から遠いなど交通アクセスの悪い立地条件になると、上記に挙げた目安以上に値下がりするケースも少なくありません。
まとめ
不動産の売買では、築年数を参考基準にするとともに、立地や市場動向を総合的に判断することが重要です。また、法定耐用年数と実際の使用可能年数の違いを理解し、物件の価値を正確に評価することが成功の鍵となります。
最後に
いつも多くの方に弊社をご利用いただき、まことにありがとうございます。弊社では引き続き売却物件も募集しています。弊社受任物件には設備保証が付きますので、ぜひエージェント:畑中隼一郎へご相談ください。
仲介手数料ですが、ご購入もご売却も割引~最大無料となります。
ご売却の場合、1億円のご自宅を売却する場合の仲介手数料を上限金額「168.3万円(税込み)」として設定しています。1億5,000万円でも2億円でも仲介手数料は「168.3万円(税込み)」です。高額のご自宅を売却するお客様には今まで以上のチャンスです。
現在多くの方にご利用いただいております。詳しくはエージェント【畑中隼一郎】にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。
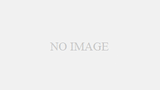
コメント