こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】のエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。
今回のブログでは、2025年4月に予定される建築基準法の改正について、書かせていただきたいと思います。

(写真はイメージです)
建築基準法とはどんな法律なのか?
「建築基準法1条」では、以下のように定められています。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする
建築基準法の規制は「単体規定」と「集団規定」
建築基準法による規制は、「単体規定」と「集団規定」の2つに大別されます。
単体規定
単体規定とは、建築物の構造的安全性や防火と避難、健康で快適な生活など建築物の安全性と衛生を確保するための規定です。地域を問わず、全国の建築物に適用されます。
具体的には、下記のような項目が「単体規定」の規制対象となります。
- 敷地に関する規制
- 構造耐力に関する規制(耐震基準など)
- 防火・避難に関する規制
- その他の一般構造・設備に関する規制
集団規定
集団規定とは良好な市街地環境を確保するための規定です。都市計画区域および準都市計画区域に存在する建築物についてのみ適用されます。
具体的には、下記のような項目が「集団規定」の規制対象となります。
- 接道規制(道路に関する制限)
- 用途規制(用途地域に関する制限)
- 形態規制(建物の容積率・建ぺい率などに関する制限)
【2025年4月施行】建築基準法・建築物省エネ法改正
2025年4月から、改正建築基準法および改正建築物省エネ法が施行されます。
改正の目的
今回の建築基準法・建築物省エネ法改正の目的は、建築物分野における省エネ対策を加速させること、および木材利用を促進することです。
国際的な枠組みにより、「2050年のカーボンニュートラルおよび2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)」の実現が目標に掲げられています。それらを踏まえて、政府は2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化しました。
建築物分野は、日本におけるエネルギー消費の約3割、木材需要の約4割を占めています。建築物分野における省エネ対策と木材利用の促進は、上記の目標達成を目指す上で効果が大きいと考えられるため、建築基準法および建築物省エネ法が改正されることになりました。
今回の改正では、すべての新築住宅に省エネ基準が適用されることや、中規模以上の木造建築物の構造計算基準変更、大規模木造建築物の防火規定緩和など、さまざまな点で建築基準が見直されます。
また、既存不適格建築物に対する規制の一部免除も行われ、空き家の再利用が進むことが期待されています。
改正の3つのポイント
1.4号特例の見直し・縮小
建築物の省エネ基準や構造安全性基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保するため、いわゆる「4号特例」の見直し・縮小が行われます。これまで、「2階建て以下」「延床面積が500㎡以下」の木造住宅など一定の条件をクリアする建物については、建築確認申請において構造に関する審査が省略される「4号特例」が適用されていました。この特例により、小規模な住宅の新築やリフォームがスムーズに進められる一方で、耐震性や安全性が十分に確認されないまま建築されるケースもありました。
この点を踏まえ、今回の改正では小規模建築物について建築確認審査の一部を省略できる「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」へ再分類されることになりました。
【新2号建築物】
従来から全ての項目が建築確認審査の対象となっていた建築物(2号・3号建築物)と、従来の4号建築物のうち以下の要件のいずれかに該当する建築物です。
- 木造2階建て
- 延べ面積200㎡超
「新2号建築物」については、建築確認申請を行う際に、省エネ基準および構造安全性基準への適合性を示す図書の提出が必要となり、従来よりも建築確認申請時の審査項目や提出書類が増えることになります。
【新3号建築物】
従来の4号建築物のうち、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物です(木造・非木造を問いません)。「新3号建築物」については、従来の4号建築物と同様に、建築確認時の審査項目が一部免除されるほか、省エネ基準および構造安全性基準への適合性を示す図書の提出も不要とされています。
2.構造規制の合理化
(a)木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
(b) 階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化・二級建築士等の業務独占範囲の見直し
3.省エネ基準への適合義務化
従来は、省エネ基準への適合が義務付けられているのは、非住宅かつ300㎡以上の中規模・大規模建築物に限定されていました。また、300㎡未満の住宅および非住宅については説明義務のみ、300㎡以上の住宅については届出義務のみにとどまっていました。
建築物の省エネ化を促進するため、原則として全ての新築住宅・非住宅について、省エネ基準への適合が義務付けられることになります。
新たな省エネ基準適合義務は、2025年4月以降に着工される建築物について適用される予定です。
また、省エネ基準への適合義務は、建築物を「新築」する場合に加えて、「増改築」を行う場合にも適用されます。従来は、増改築時には既存部分を含めた建築物全体について、省エネ基準への適合性が判定されていました。しかし今回の建築基準法改正では、増改築部分だけで省エネ基準への適合性が判定されることになった点に注意が必要です。
省エネ基準への適合を確認するためには、「新3号建築物」を除き「エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」を受ける必要があります。省エネ適判は、所管行政庁(市町村長もしくは都道府県知事)または国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関が行います。
まとめ
ここまで、ご一読いただきありがとうございました。
2025年の建築基準法改正により、「4号特例」の見直しが行われ、「省エネ基準」も強化されることになったため、これまでの建物よりも環境にやさしく、より安心・安全な建物が建築されることになります。他方で、建築費・リフォーム費用がこれまでよりも高額になってしまいます。これから建物を建てる方、リフォームを行おうとお考えの方は、従来よりもコストが上昇することになる可能性にご留意ください。
では、また。

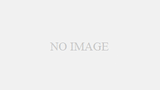
コメント